ウィーン・フィルが日本に来ています。ティーレマンと。ぶいぶい言わせているに違いないと思っています。じゃあウィーン・フィルがいないあいだ、母体であるウィーン国立歌劇場はどうしてんの、と思った人はおられますか。いませんか。ウィーンなんてどうだっていいのか!
そんなけったいなこと言いなはんなや。
本当の事をいうと、ウィーン・フィルが出かけていてもウィーン国立歌劇場は通常営業なんですね。ウィーン国立歌劇場は毎日営業、毎日違う演目を上演。それだけでもげえっなのに、そのうえ、ときどきオーケストラの一部がウィーン・フィルと称してツアーにでかけたり、コンサートの定期演奏会をやったりしているわけです。彼らは昼夜2公演とかも普通にやっていたりします。
はっ。
ここで私は気がつくわけだ。働き方改革という言葉が必要なのはウィーン・フィルやウィーン国立歌劇場では?詳しい労働環境を知っているわけではありませんが、オペラ上演、コンサート、リハーサル、つまり本番やリハで自分の時間を拘束されるだけではないんで、その裏でどれだけ個人練習をしているのか、事務方はその準備をしているのか、などと考えると、ブルブルブルブルと私はす震えざるを得ないのです。しかしそのあたりはきっとなにかうまく考えられているのでしょう。
ウィーン国立歌劇場は第二次世界大戦で爆撃に遭って破壊されたことはご存じでしょうか。ベーム(当時の大指揮者)とかも破壊された劇場を目にしてガビーン!していたということなんですが、10年かけて再建され、1955年11月5日に再オープンしたのです。つまりいまから70年前。
そういうわけで記念の式典が行われ、ナチス政権下でこの建物で働いていた犠牲者を追悼する記念のプレートが序幕され、歌劇場の中では来年1月まで記念の展示が行われているのです。バルコニーにて、なので、ウィーン国立歌劇場のチケットを持っている人なら誰でもみられるよ。破壊から再開までの10年間のみちのり、その復興の様子の写真、オブジェ、解説文。また記念の書籍も発売されたとのこと。写真もいっぱい載っているのでしょう。
破壊、再生、そして未来へ。これからの70年もさらにウィーン国立歌劇場が輝いていますように。
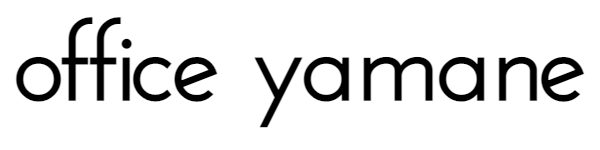





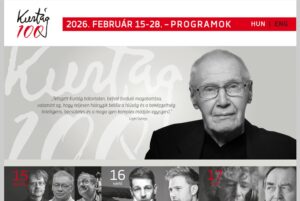
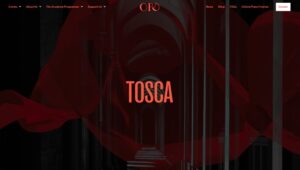




コメント