ストリーミングは不思議だという話を聞くことがあります。いわゆる一般的な、フィジカルとかそういう業界用語的な感じの言葉もありますけれど、CDなどとは動きがかなり違っていることがあるのだそうです。
実際先日、ストリーミングに関するあるデータを見せていただく機会があったのですけれども、こういっては何だが、意外なと思われるような国で熱心に聴かれていて、ほよー、ほよよー、ほよよよー、と思ったのでした。そういうもんけ。そういうもんみたいなんよ。世界中でアベイラブルなわけだから、誰がどこで耳にしているかわからない。それが具体的に地域別で可視化されると、けっこう面白いですね。
クラシック音楽のストリーミングサービスで、世界でもっとも巨大なのはアップル・ミュージックでしょうかスポティファイでしょうか。どっちがでかいかは不明ですが、ともかくどちらも大きいことは間違いがございません。
そのアップル・ミュージックで今年最も聴かれたのは(まだ11月だが今年とくくっちゃうのはなぜ、という単純な疑問は横においておくとして)、なんとアリス・オットの弾いたジョン・フィールドの夜想曲集なのだそうです。
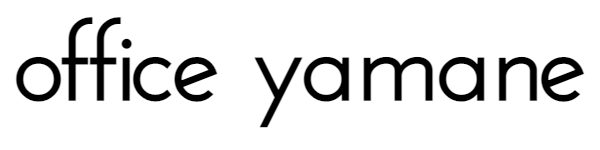






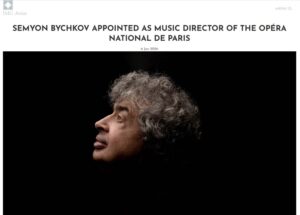
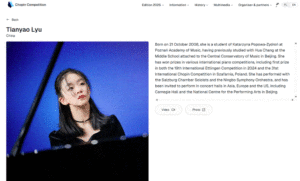

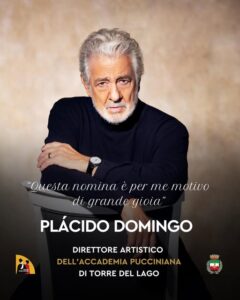

コメント