こうして戦後80年が経過しても、新しい発見があるというのは驚くべきことですね。ハンガリーの美術商が購入した楽器、何年もそのままに保管されていたヴァイオリンを修理に出したところ、とんでもない事実がわかったという話です。
依頼を受けて専門家が修理を始めたところ、明らかに熟練した人物の手によるものだということがわかったものの、どうしてこんなに粗悪な木材が使われているのかが理解できなかったという。そこで、その矛盾に突き動かされた専門家がヴァイオリンを分解したところ、製作者の秘密のメモが露わになったという。
製作者はポーランドのユダヤ人、フランシス(フランチシェク)・ケンパという1903年生まれの人物で、かすれたメモには「工具も材料もない厳しい状況下で製作された試作品。ダッハウ。1941年、フランシス・ケンパ」とシレジア語で書かれていたというのです!!(上の画像がそれ)
ダッハウの強制収容所にはいくつか楽器が持ち込まれていたことは知られていたものの、収容所で作られたのはおそらくこれが初めてのケースだったのではないかということだそうです。ダッハウの強制収容所記念館に連絡をとったところ、ケンパのヴァイオリン製作の技術はナチスも知っていて、それが収容所を生きて出られた決定的な要因だったのではないかと考えられるとのこと。
ケンパは戦後ポーランドに戻り、1953年に亡くなるまで楽器を作り続けたのだそうです。
美術商のタロシは「これを『希望のヴァイオリン』と名付けました。困難な状況に陥っても、課題や挑戦があればそれを乗り越えられるのです。問題ではなく、課題そのものに集中できるのです。この楽器製作者が強制収容所を生き延びることができたのは、それが役立ったのだと思います。」と語ったという。
希望のヴァイオリンとわざわざ名付ける必要はないと思うのですけれど、しかし、一人一人の人生とは本当に貴重で、かけがえがなく、替えが利かないものなのだという思いを新たにさせられます。上のリンクにはほかにも画像が掲載されているので、ぜひ見てきて、歴史の重みを感じてください。
それにしても今朝、早朝のウォーキングをしていたら穏やかな、しかし左手のないおサルさんに道で行き会い、しばらく心の交流をした(と思っているのは私だけだろう)のもまた、かけがえのない体験であった。一日一日を大切に生きよう。とりあえず洗濯を干そう。
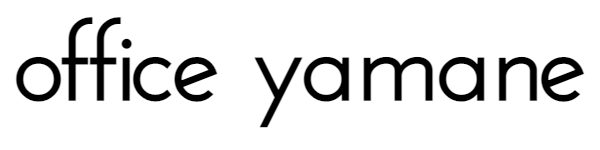






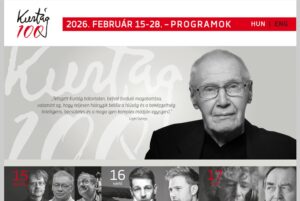
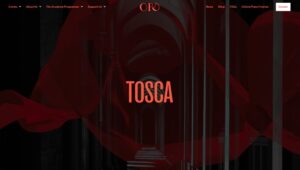



コメント