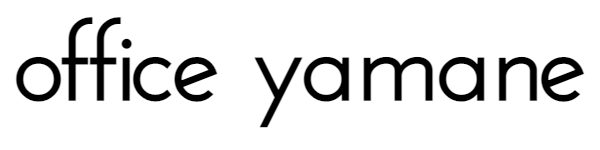2025年10月7日(火)於:東京文化会館
東京都交響楽団の新しい指揮者陣が発表となり、やややっ!!意外な!と思われる人選もあったため、これは話を聞かねばと思い、都響の芸術主幹を2013年より務めておられる国塩哲紀さんを訪ねました。
詳しくはこちらをご覧下さい:
2026年度からの指揮者体制について(東京都交響楽団ニュース、2025年9月24日付)
新体制の発表──意外な人選の理由
さっそくですが、お話を聞かせてください。わりと少なからぬ方が「そうきたか」と思われたと思うのですが、首席指揮者としてペッカ・クーシスト(1976- フィンランド。ヴァイオリニスト・指揮者・作曲家)が2028年4月から着任されるとのこと。ずばり、なぜクーシストなんでしょう。

「業界を衰退させないため」ですよ。
出た!衰退業界。それは某楽団の広告の見過ぎでは?
いやいや、真面目に言っています。衰退させないためペッカ・クーシストのような人が必要だと思ったのです。山根さんは発表を見てどう思ったんですか?
意外な名前だな、と。
誰も予想していなかったでしょうね。
で、これが業界衰退とどう繋がっていくんですか。
私も、最初からそんなことを考えていたわけではありません。今の音楽監督である大野和士もいずれ任期満了になる、次はどうすべきかな、と何年も前から考えているうちに、現在の都響の指揮者たちは、長年にわたって良い音楽作りをして都響を発展させてくれ、支えてくれているし、関係も良好だから、それはそれで何らかの形で継続してもいいんじゃないかなって気持ちも生まれてきた。しかし、そうすると、また同じような人が次の首席指揮者とか音楽監督になったら、あまり意味がないかもしれないと思ったんですよね。

「衰退」させないため必要な新しい風、硬直化しないための直感
言葉は悪いですがマンネリを避けるということですか?
クラシック音楽の魅力や存在価値は永遠に不滅ですが、なにしろ日本は人口が減っていくので、放っておけば、マーケットとしては静かに縮小していくのは否定できないでしょう。だから、新しい何かを考えないといけない、それは別に変わったことをするという意味ではなく、時代の変化にも対応できる柔軟性を持たないといけないという意味です。
さっきも言いましたが、都響ではここ十数年、大野和士、アラン・ギルバート、小泉和裕、エリアフ・インバルという素晴らしい指揮者たちが、それぞれのスタイルで都響を率いてくれています。で、ふと考えると、みなさん音楽的には重厚。だから、彼らとも関係を継続するとなると、この上同じタイプの指揮者が来ても、同じようなレパートリーを重ねて繰り返すだけになる。指揮者によって異なる解釈が聴けるのがクラシックの良いところと言っても、プログラムの調整は大変になるし、何より、オーケストラが少しずつ硬直していくかもしれない。それは避けたいと思った。

そう考えていたら、2024年4月にペッカ・クーシストが都響に客演して、ベートーヴェンの交響曲第7番を指揮したんです。その演奏がほんとうに素晴らしかった。実にクリエイティブで、彼自身も心から楽しんでいたし、楽員たちものびのびと演奏していて、オーケストラの音がいつも以上に生き生きしていた。その瞬間に、「ああ、こういう人がシェフになったら面白いだろうな」と。もう理屈じゃなくて、ひらめきに近かったですね。
彼を2024年4月のプロムナードコンサートに指揮者として招くことは、2022年12月に決めていました。もちろんその時はシェフの候補かもなどということは全く考えていませんでした。で、いざヴィヴァルディ「四季」を弾き振りし、ベートーヴェン7番を指揮し、演奏会は大成功。終演直後、舞台袖で矢部達哉(ソロ・コンサートマスター)が「彼が首席客演というのもいいかも」と話しかけてきて、私は反射的に「いっそ首席でもいいと思います。マーラー、ブルックナーの指揮者は都響にはたくさんいるから、新しいタイプとして」と返しまして(笑)。そのあと、クーシストと楽屋でいろいろ話している時、どうしようかなと思ったけど、思い切って彼に「都響の指揮者になってくれませんか」とお願いしました。彼はびっくりしていましたけど、とても喜んでくれた。それから1年以上かけて細かい話を詰めたわけですが、その場で彼の気持ちはほとんど固まっていたと思います。
本当は私一人でこんなふうに決めてはいけないのかもしれませんが、だからと言って改めて会議や投票などやっても誰もが納得するような結論が出るとも思えませんし、何よりチャンスを逃すかもしれない。責任を取る覚悟で、自分の直感に従いました。

直感ですね。直感で決めるな、と思われる人もおられるかもしれないのですが、こういう閃き、「びびっと来た」みたいなものって、長年の経験やそれに基づく知識やなんかがあって、かついろいろと考え抜いた結果最後にやってくるもので、そういう瞬間って実はめちゃくちゃ貴重だったりしますよね。
オーケストラって、変化がすごく難しい組織なんですよ。大きな石を動かすようなもので、一気に方向を変えようとするとどうしてもひずみが生じる。だから、無理にドラスティックな変化を起こす必要はない。都響はすでに優れたオーケストラ。これまでのカラーは大切にしながら、そこに新しい色を少しずつ重ねていく。そのほうがいいのではないかと思ったんです。
変化、しなやかに
大きな石をゆっくり動かす、という表現、とても分かりやすい喩えだと思います。
つまり「しなやかに」変化させると言いましょうか。これまでの指揮者たちが、揺るぎない都響の響きを作ってくれた。彼らとの関係はこれからも続くし、立場が変わっても協力し合える。その上で、ペッカ・クーシストやダニエーレ・ルスティオーニのような、もう少し若い世代で、違うパーソナリティや音楽的キャラクターを持った人たちが加わり、都響自身も世代交代しながらよりいっそう柔軟になっていきたい。それが、衰退を避けるために必要なことだと考えたのです。
ルスティオーニ(2026年より首席客演指揮者に就任予定)についてはどうだったのでしょうか。

ルスティオーニとは、2014年に二期会オペラ「蝶々夫人」での初共演から意気投合し、その後も定期演奏会に出演してもらっていましたが、彼自身がリヨン国立オペラの首席指揮者やアルスター管弦楽団の音楽監督も務めながら世界中のオペラハウスを飛び回っていて、なかなか時間が取れなかった。でも今から2年ほど前、マネジャーが「近い将来少し時間ができそうだ」と言うから、すぐに「では都響と新たな関係を築きませんか」と首席客演指揮者のポストを提案しました。アラン・ギルバートの後任も考えなければならない頃だったので、ちょうど良いタイミングでした。
なるほど、よい関係が続いていた。そしてタイミングもあった。重要ですね。
若い世代とともに──新しい都響の姿
いろいろなオーケストラを見たり聴いたりしながら指揮者のことを考える中で、だんだん思うようになったのは、ここらで“ゲームチェンジャー”が必要だ、ということ。思いがけない発見をくれる存在、予想外の方向に連れて行ってくれる存在。そういう人がいると、組織が活性化する。ひいては業界も発展する。あるいは話題性。シェフに若手を抜擢するオーケストラが増えているのも、そういう傾向の一つの表れではないでしょうか。
都響に限らず、演奏家、特に今の若い世代の演奏家は、「こうしろ」と言われて動くことを好まないでしょう。むしろモチベーションを高めて、主体的に能力を発揮してもらうことが大事かと。だから指揮者も、音楽でみなをリードし、コミュニケーションも大事にしてくれる人がいい。その意味でクーシストは適任だと思っています。音楽家としてレベルが高く、人柄も良く、音楽を「生きた瞬間」として共有できる。一緒に演奏することがプレイヤーたちにとっても、クーシスト自身にとっても、いつでも新鮮な刺激になることを期待しています。
それが都響にとって何よりの財産になると。
それからもう一つ。近年、オーケストラコンサートの人気レパートリーの中心は、マーラー、ブルックナー、ショスタコーヴィチ。かつてに比べると現代寄りになったし、広がりもあります。一方で、オーケストラというのはコンテンツとして完成されてしまっていますから、人気があるからと言ってそれらをただ繰り返すだけでは、オーケストラも聴衆もそのうち慣れてしまって、飽きてしまう危険があります。演奏会がいつの間にか何の工夫もないただの博物館みたいになってしまってはいけない。だから、オーケストラには、芸術性を保ちつつ、“柔軟さ”と“冒険心”も必要だと思います。クーシストの、既成概念にとらわれない、ボーダレスなアイデアが、都響の可能性をよりいっそう広げてくれるのではないかと思っています。
楽員の皆様の反応はどうだったのでしょうか。
楽員には、去年(2024年)のうちに指揮者人事の具体的なアイデアについて説明しました。表立っての異論や反論はありませんでしたが、戸惑ったかもしれませんね。なにしろベートーヴェン7番でしたから、実際にクーシストの指揮で演奏した楽員は限られていましたので。
発表後、外部の反響はいかがでしたか。
国内外から驚きや好評などいろいろ反響がありました。どちらかと言えば海外のほうが、クーシストの知名度の高さもあってか、反応が大きかったですね。海外のマネジャーや指揮者やオーケストラから「見たよ、いいね!」「面白い」というコメントがいくつも届きました。別に奇をてらったわけじゃないけど、サプライズだったようです。それだけでも価値があると思う。これからは、その期待に応えていかなければなりません。

ネガティブな反応についてはどうでしょうか。
ネット上では見かけますよね。まあ、何をやっても批判する人が現れるのは仕方ない。今回の指揮者人事も、戸惑う方はいらっしゃると思います。クーシストは指揮できるの?とか、そもそも知らないとか。知らない名前だから行かない、という人もいるかもしれない。でも、まず一度聴いてほしい。聴いて好きになれなかったら、それはそれでいい。聴く前から拒否してしまうのはもったいない。
逆に、「ペッカが来るなら聴いてみよう」「会員になろうかな」と言ってくださる方もいます。クラシック音楽以外のジャンルにも彼のファンがいますからね。そういう方たちが都響に、そしてオーケストラに関心を持ってくれるとありがたい。新しいお客様が増えることで、聴衆の層が広がってほしいと思います。
常に新しい人、顧客を呼び込んでいく、それはどの業界でも絶対に必要な真実だと私も思っています。
偉そうなことを言いましたが、こんなことは業界の誰もが長年考えていて、いろいろな方法で努力しています。これからもそういう努力と工夫の積み重ねあるのみです。
指揮者の肩書きに込められた関係性
ありがとうございました! ところでここからは雑談ですが。指揮者の肩書きって、どのオーケストラを見ても本当にさまざまで、複雑ですよね。肩書きにはどういう意味があるんでしょうか。
あー、確かにわけわかんないですよね(笑)。まああれは、オーケストラごとに歴史や事情があって決めているものだと思います。一般的には「音楽監督」「首席指揮者」「常任指揮者」などいろいろありますけど、その意味や役割は国や楽団によって異なりますし、例えば「音楽監督」と「首席指揮者」はどう違うのかなんて、明確に区別することは難しいです。さらに、「音楽監督」「音楽総監督」「芸術監督」「アーティスティック・アドヴァイザー」…きりがない(笑)。日本では「音楽監督」といっても人事権まで持っているケースはまずありませんし、現場の実質的な運営はまた別の人が担っていたりします。
英語でも“Chief Conductor”とか“Principal Conductor”といった呼び方があって、国によって、あるいはオーケストラによって違ったり、どちらでもよかったりする。しかも面倒なことに、日本語だとどちらも「首席指揮者」になってしまう(笑)。さらに「常任指揮者」とはどう違うのか?…わかりません(笑)。それどころか、ある指揮者を迎えたいために新しい名称のポストを作ったりもする。だから、世界的に統一した名称や定義を作るのはほとんど不可能だと思いますね。
無理か。残念。
結局、指揮者の肩書きというのは「どういう関係性を築いていきたいか」を表しているだけだと思うんですよね。どれだけの時間をそのオーケストラのために割けるか、割きたいか、割いてほしいか、などにもよるし。指揮者の側から「こういうタイトルで活動したい」と言われることもあります。そのあたりは話し合って、双方の思いが重なってタイトルを決めているはずです。超一流オーケストラのポストともなると、時には指揮者のマネジャーたちとオーケストラとの政治的駆け引きも絡んできますしね。ですから、肩書きの裏には、その時代やオーケストラの事情、そして指揮者との関係が反映されているんだな、ぐらいに思って、あまり気にしないでください(笑)。
フレンドオブでもなんでもありということですね。今日は長時間にわたりありがとうございました!
(了)